自分が実現したいビジョンの答え合わせが 確かにできる「オランダスタディツアー」
- 20-30代
- 後継者
- 新規ビジネス
- イベントレポート
この記事は11分で読めます

創業大正11年(1922)佐賀県嬉野市にある五町田酒造株式会社は、東洋一の酒を目指すという気持ちを込めた清酒「東一」を醸造する酒蔵だ。「米から育てる酒造り」をかたくなに守る三代目社長の瀬頭一平氏のもと、地元を大切にしながら102年の歴史を刻んでいる。取締役の瀬頭結美氏は、それまでつくっていた日本酒とは違う味わいの、洋食にもあう「Lieto(リエート)」を開発。新しい酒の楽しみ方を提案し、日本酒ファンのすそ野を広げている。

五町田酒造は、1988年に佐賀県で初めて酒米・山田錦の栽培を手がけ、試行錯誤を繰り返しながら、数々のコンクールで入賞する銘酒「東一」を作りあげ、全国に届けている。
「山田錦は、台風の多い佐賀での生育が難しく苦労が多いと想定され、最初はどの農家さんに頼んでも断られたそうです。それでもどうしてもこの酒米が必要だと兼業農家であるわが社の蔵人に頼んで育ててもらったと聞いています」
今では、協力してくれる農家も増え法人化を果たし、山田錦を栽培する田んぼは、20町を超えたと結美氏は言う。
「蔵人は、自分たちが精魂込めて育てた米で酒造りをしています。その想いの深さはけた違いだと思います」
五町田酒造には、「人・米・造りが一体となって良酒を醸す」という強い経営理念がある。
「ここで言う、“人”は、酒造りに携わるすべての方を指しています。蔵人以外にも販売店の方、提供してくださる飲食店の方も含めたおひとかたおひとかたが、『東一』という酒を造ってくださっているという感謝の想いがここにあります」
“米”は自分たちの手でつくることにこだわっている。酒造の周りに広がる稲田の風景が誇りで、休耕地にするくらいなら、山田錦をつくってくださいとお願いし続けた賜物だという。
「最後の“造り”は、100年以上積み重ねてきた技と時代と共に変化する味わいを作り出す技術や知恵を集約した言葉です。これらの3つが一緒になって初めて良い酒が造れるのだと信じて日々取り組んでおります」
コロナ禍において、吟醸酒造りにこだわってきた「東一」に新たな味わいの酒を加えたいと結美氏は考えた。それが普段日本酒をあまり飲まない人にも選ばれるようにと醸造した「Lieto(リエート)」だ。
「洋食にも合う酒をコンセプトに、コロナ禍での経験も踏まえて気持ちが少しでも明るくなるような商品をと考えました」
最初は、「東一」らしくない味わいに反対していた瀬頭社長だった。
「これを飲まされたら、なんじゃこれはと自分なら思ってしまうと辛辣な言葉も投げかけられました」
しかし製造部長の高木大輔氏が「女性の感性を生かした味があってもよいのでは」と後押しをしてくれた。
「今の時代の食生活に合わせるには『東一』らしさを残しながら、進化させていきたいと言ってもらい、一緒に相談をしながら味の方向性を決めていきました」
瀬頭社長も「高木部長がそう言うなら」と、最後は同意し「やってみたらいいんじゃないか」と言ってくれた。
「こうして2023年、軽い飲み口の進化した日本酒『Lieto(リエート)』を世に出すことができました」

3人姉妹の長女として嬉野市で育った結美氏は、幼いころから周囲に「お婿さんをもらって、酒蔵を継ぐのが当たり前」だと言われて育ってきた。
「反対に両親は一度もそんなことは言いませんでした。むしろ、継がなくていいから自分の好きなことをやりなさい。後悔しない人生を送るようにと常々口にするので、その言葉に重圧を感じていました」
さらに、大学生になったら親元を離れた地に出ることが絶対条件だった。
「このまま地元にいたらずっと東一のお嬢さんとして見られる。だから見知らぬ土地に行き、社会と組織を学び、自分の力で食べられるようになりなさいと言われました。当時は心細くて、泣きたくなりました」
大学卒業後は物流会社に就職。東日本支店に配属され、国際的なものの流れや一流企業の仕組みの中で学ぶことの多い6年間を過ごした。
「自分のプロジェクトにひと区切りがついたときに、大阪本社の理事から次の仕事を一緒にしないかと声をかけていただきました」
この仕事を受ければ、向こう10年間は全国を飛び回る必要があると言われていた。
「やるなら中途半端は嫌な性格なので、おそらくそれに没頭してしまうことがわかっていました。一方、もうすぐ30歳という年齢に差し掛かり、このまま家業や実家を放っておいていいのかというモヤモヤとした気持ちもありました」
会社に対して失礼のないようにしたいと考えたり、もともとこの物流会社を選んだのは将来家業に役立つからだったじゃないかと思いあぐねたりと、自分の進路が揺れに揺れた。
「今までで一番悩んだ時期でしたが、将来への覚悟を決めたターニングポイントにもなりました」
両親からは相変わらず何も言ってこない。
「なぜ何もいってくれないんだとそれが逆にプレッシャーにもなりました」
そこで意を決して両親に相談すると「実家に戻るなんていう選択は、一番ダメだ。悩んでいるなら、会社に居続けなさい」と突き放された。

もともと3姉妹や血縁に関係なく、第三者に事業継承してもいいんだと覚悟を決めて酒蔵を経営してきた父だった。
「そんな腹の座った父を相手に半年くらい何度も話し合いました。今思うと退路を断って家業に入りたいという私の考えが、ここ嬉野の地で皆さんに受け入れられるかどうかを見極めていたのかなと思います。あのときは、私の覚悟を試されました」
ようやく「本気で出した決断なら尊重する」という言葉をもらい、酒造りを一から学ぶことからスタートした。しかし東京のスクールに入学直後、コロナ禍を機に嬉野に帰ることになってしまった。
「目の前で行われている酒造りからたくさんのことを学ぶことができて、かえってよかったと今では思います」
営業企画室という肩書をもらい、新しい販売先を増やすために営業活動を行ったり、イベントを通じた広報を担ったりすることになった。それまでは瀬頭社長が、地酒を専門に扱う全国の酒販店と丁寧に付き合いながら販路を100店舗に広げてきたのだ。
「今までのお付き合いを大切にしながら事業を広げるべきだと考える社長とそれだけでは顧客との接点が増えないという私がぶつかることもありました」
しかし、「東一」を知ってほしい。もっと多くの人に飲んでもらいたいという目指すべき方向はお互い同じだった。
「北海道と鹿児島に『東一』を扱ってくださる店を新しく3軒増やすことができました。それまで取り扱いがなかった地域へ卸すことができたときには、やはり喜んでくれていたと思います」
今では海外への販路拡大として取り組んだ台湾への輸出量が年々増えているという。

結美氏は、瀬頭社長がどの働き手に対しても丁寧に声をかけている姿を見て育った。
「やはり経営者として、理念を体現する社長を尊敬しています。社長は日々、人が一番大切であることを私たちに行動で示してくれているのではないでしょうか」
30人いる従業員の健康状態や子育てや介護などさまざまな家庭の事情を把握しながら、人員体制を組むのが経営者としての大切な仕事だと常々口にしているという。嬉野に帰ってきてみて、改めてふに落ちたことがある。
「お米づくりに始まり、地元の皆さんがとても愛に溢れた酒造りをしてくださっているのを肌で感じました。創業当時から積極的に地域雇用を大切にしてきたのは、会社がこの場所でなければ存続する意味がないからだと改めて理解できました」
酒蔵というと張りつめた空気の中で無口に働く人々をイメージしがちだが、ここでは、上からものを言うような雰囲気はどこにもなく、働いている人たちがお互いを尊重し、楽しそうに立ち動いている。
「ここ数年で代替わりもあり、雰囲気がだいぶ変わりました。蔵で働く女性も増え、場がだいぶ和らいだと思います」
約100本あった仕込みタンク本数はコロナ禍で47本まで減り、雇用を維持できないかもしれないと悩んだこともあった。現在は8割程度まで出荷数が戻ったが、日本酒を日常的に飲む人の数は減ったままだ。
「酒造りの伝統を守りながら新しいお客さまや市場に向けた次の一手を考え、『東一』との接点を持ってもらえる層を広げたいと考えています」
しかし環境に逆らい、夏場に無理に酒を造るために冷蔵設備を入れたり、機械化を進めて増産したりはしないという。
「われわれは工業製品をつくっているのではありません。あくまで嬉野の自然に寄り添う形で夏場は米を作り、冬になったらそれを仕込み、手の感覚で酒をつくることを大切にしながらやっていきます」
このバランスを見ながら、酒造りの手法を守るのも経営者の大切な役目だと教わった。
「家業が農業にも携われる酒造りでよかったなと、先祖に本当に感謝しています。暮らしに寄り添いながらつくっている酒なんだというこの誇りをもっと多くの方に伝えたいです」

結美氏が家業に入るにあたって不安だったのは、これまで組織で培ってきた人間関係や人脈がいったんリセットされて、相談したい時に話せる相手がいないのではということだった。
「それは杞憂(きゆう)でした。前の会社の方や同業の蔵元で同年代の方とも話す機会が多々あり、意外にも相談する相手は全国にいるとわかりました。今では、すごく勉強になっています」
そんななか、J300アワードという女性社長が選ぶ女性社長のためのアワードにでてみないかと声をかけられた。
「こういうものに参加するのは初めてだったのですが、自分の視野を広げるチャンスだと思いました」
エントリーシートを記入することで自分のこれまでを振り返る良い機会にもなった。
「今のままだと良くも悪くもこの業界や地域に染まっていってしまう。自分が井の中の蛙になっているのではという不安がありました」
ほかの女性経営者が何にチャレンジし、どういう志をもち、なぜ取り組んでいるのかを知り、大いに刺激を受けた。プレゼンでは、自分なりに考えた「東一」の将来への提案が評価され、「後継ぎウーマン賞」を受賞した。
「日本酒に出合う入り口として、酒粕のコスメや、宿泊して楽しむ利き酒体験などを企画して『東一』ファンを増やしたいと訴えました。この業界で次の展開をどうするかを考えていましたが、背中を押していただいたと思います」
酒造業界の常識では考えられないようなことにチャレンジしていきたいという姿勢が認められたと感じている。
「自分で会社を立ち上げ、新しい事業に挑戦している女性経営者の方々を拝見し、私も日本酒の売り上げ低迷くらいでめげてちゃいけないなと思いました」

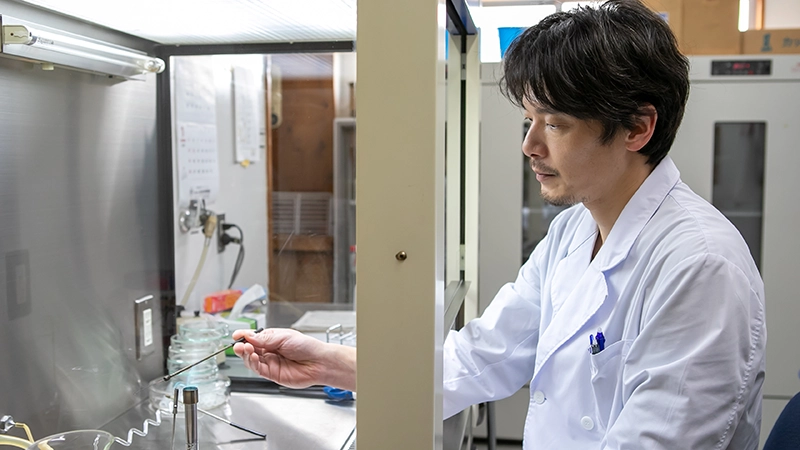
今も両親からは、会社を継いでほしいという話はない。相変わらず跡を継ぐのは血縁の者でなくてもいいと考えているようでもある。そして周囲の人々は結美氏が社長になるとは思っていないようだ。
「婿を早く取れ、次の代の後継ぎをなどの声が聞こえてきます。仕事は頑張っていればいいのですが、プライベートなことを言われると悩みます」
ここでも両親は、「気にすることはない」と言ってくれている。
「入社して3~4年経った時に、経営側として皆さんの前で判断ができるようになってきたと社長に認められ、そろそろいいだろうと取締役になりました」
次は社長から「任せたよ」という言葉をかけてもらえるように、実績を積み重ねたい。
「父が安心して交代を口にできるように、しっかりした結果をだしていきたいのです」
現在、新規開拓の営業活動は、「任せた」と言ってもらえている。その言葉が、経営のあらゆる場面で聞けるようになることが4年後の目標だと自分に課している。
「どっしりとしたうまみがあるクラシックなタイプの『東一』のファンのすそ野を広げること。『Lieto(リエート)』のような洋食にも合う軽い飲み口の新しい日本酒を開発し、知ってもらい新たな日本酒ファンを作り出すこと。この両軸をアクティブに手がけられるのは私しかいないと思っています」
やってみたいことは、山ほどある。たとえば今でも県内の配達は自社で行っている。ほかの酒造メーカーから見れば後発のブランドだという自覚があるからこそ、店主の顔を直接見て、頭をさげて注文を取ってくるという姿勢を貫いてきた。
「その営業担当の人数が減っていたのをテコ入れしたいです。酒販店も代替わりの時期を迎えていて、廃業してしまう店や次の世代に新しい形の経営を託す店が出始めています」
だからこそ今以上に出向いていき、濃いコミュニケーションをしたいのだという。
「海外にも直接足を運びます。ゆくゆくは大きな市場であるアメリカでの販売拡大も視野に入れています」
五町田酒造の「人・米・造りが一体となって良酒を醸す」という理念を結美氏も貫く覚悟だ。その姿勢をこれからの酒販店拡大に、新しいファン獲得に、海外市場開拓に生かせる日が来るのもそう遠くはなさそうだ。
お客さまの声をお聞かせください。
この記事は・・・